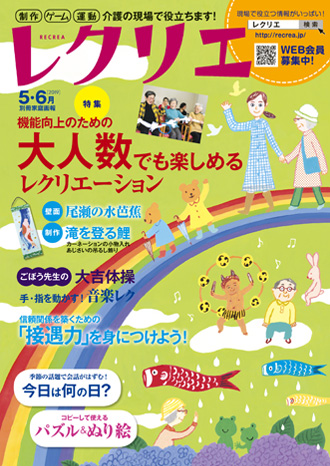事例で学ぶ認知症ケア
「パーソン・センタード・ケア」で考える認知症ケア
「パーソン・センタード・ケア」とは、認知症ケアには欠かせない考え方の一つです。BPSDのある人もこの考え方をもとにかかわることで、“その人”に寄り添ったケアを行うことができます。
現象だけにとらわれず“その人”を見るようにしましょう
介護者は、認知症の人を見る時、BPSD(行動・心理症状)のある人には、どうしたらケアがスムーズにできるかと考えます。一方で、静かにじっと座っている人には、ケアがうまくいっていると安心します。しかし、この時、見ているのはいずれも「現象」に過ぎません。認知症の人自身に目を向け、思いを寄せているわけではないのです。
「パーソン・センタード・ケア」は、“その人”を見てかかわる大切さを示した、認知症ケアには欠かせない考え方です。英国の故トム・キットウッド教授によって提唱されたもので、認知症の人に対し「その人本人が、自分を取り巻く人々や社会とかかわりを持ち、人として受け入れられ、尊重されていると実感できるようなケアを行っていくこと」を求めています。つまり、背景まで含めて利用者を人としてとらえ、本人の思いをくみ取り、心に届くケアをするということです。
パーソン・センタード・ケアを行うにはアセスメントが重要。その人の個性や生活歴を知り、現在起きている現象の理由を推察するようにします。認知症の人は、一般的に自分の思いや意思をそのまま行動に移すことが不得手です。介護者は利用者の言動に対処するのではなく、裏に隠された“その人らしい”生き方や価値観を洞察する力が必要です。その力が、必ずよい結果につながっていくでしょう。
現象にとらわれたケア
車いすの利用者が立ち上がって、手すりを持ち歩こうとしています。その「現象」だけを見てしまうと、転倒を起こさないことが最優先になり、その人がなぜそうしているのか、本人の思いが置き去りになってしまいます。
本誌では「パーソン・センタード・ケア」で考えた“その人” を見たケアについて具体的に解説しています。
社会福祉法人浴風会本部浴風会ケアスクール校長、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員。障害者福祉の地域実践を経て、老人福祉施設の立ち上げ・運営に30年余携わる。著書に『認知症ケアの真髄』がある。
文/高野千春 イラスト/ホンマヨウヘイ