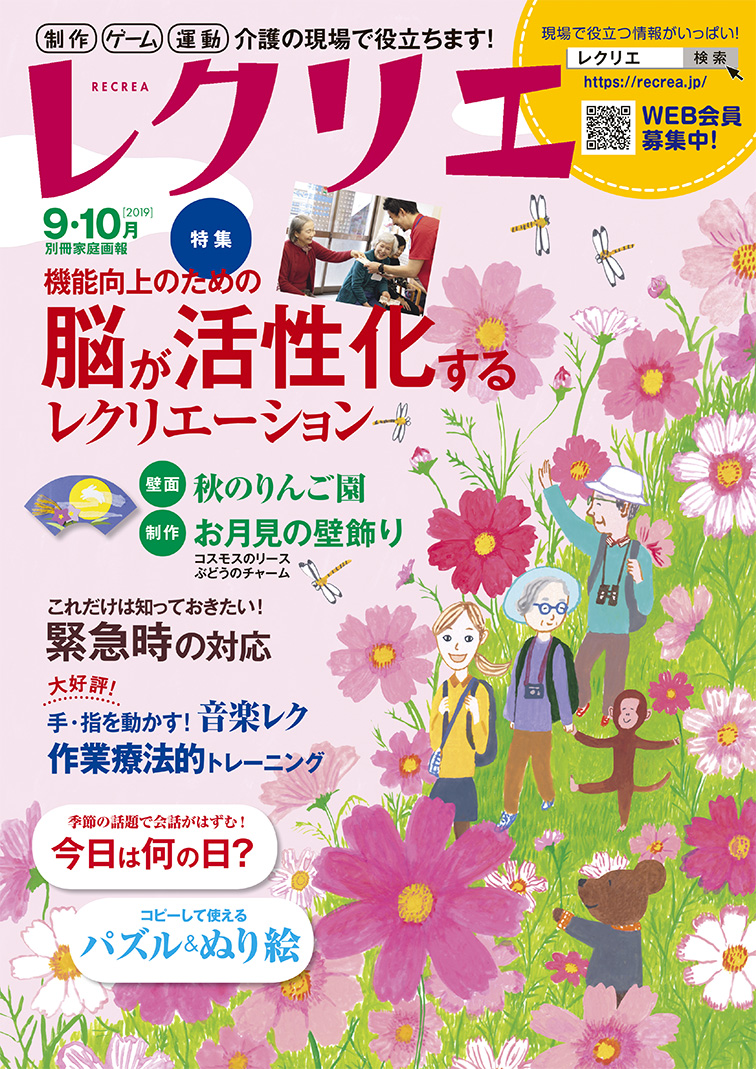事例で学ぶ認知症ケア
事例で学ぶ認知症ケア〜頻繁にトイレに通う⼈への対応
トイレに行ったばかりなのに、またトイレに行きたいと言う──これは、認知症の人に多くみられる行動です。介護者には面倒に感じられ、対応にも苦慮することが多いのですが、かかわり方によっては頻度を減らすことが可能です。原因を探ることから始まる、そのかかわり方をみていきましょう。
身体機能の低下のほか心理面に要因があることも
トイレに頻繁に行きたがる原因としては、まず認知症による記憶障害が挙げられます。また、老化による排尿機能の衰えによって、膀胱に残尿があったり、尿道括約筋(かつやくきん)が緩んでいることも考えられ、これらは身体的要因による頻尿といえます。
その一方で、心理面に要因がある場合もあります。例えば、寂しさから、だれかにかまってほしかったり、過去の排泄での失敗経験から神経質になっていたり、自身の体験や周囲の環境、あるいは認知症の影響によるものだったりなどです。この場合、トイレに行くことが自分の気持ちを落ち着かせるための手段になっています。
頻繁にトイレに行きたがる利用者については、まず身体的に問題がないか、きちんと診察を受けてもらうようにします。問題がない時は、心理面の要因を疑います。
とはいえ、心理面の要因を探るのは容易ではありません。どんな時に訴えがあり、どんな時にないのかを、普段から観察することが必要です。また機会を設けて利用者の話を聞くようにすると、そこにヒントが隠れているかもしれません。
どうしても要因がわからない時は、声かけやタッチングなど短い時間でもかかわりを持ち、見守られていると感じてもらえるようにして様子をみましょう。スタッフ間で情報を交換しながら対応を検討していくことが大切です。

こんな人も頻繁にトイレに行きたがる傾向に
[人に頼れないタイプ]
紙パンツのはき替えを、スタッフには頼みたくないという人がいます。でも、紙パンツの状態は気になるので、そのたびにトイレに行きたいと訴えることに。何でも自分でやってきた自負を持っている人に多いケースです。
[潔癖なタイプ]
清潔にこだわる人が、過去に粗相をして下着を汚した体験をくり返したくないという思いから、トイレに通います。羞恥心に加え、汚れた下着の気持ち悪さや不潔感が耐えられないという思いがあることも。
本誌では、頻繁に尿意を訴えるシーンを想定した事例のワークシートを紹介しています。
社会福祉法⼈浴⾵会本部浴⾵会ケアスクール校⻑、⽇本⼤学⻭学部医療⼈間科学教室 ⾮常勤講師、社会福
祉⼠、精神保健福祉⼠、介護⽀援専⾨員、アドバンスソーシャルワーカー。障害者福祉の地域実践を経て、
⽼⼈福祉施設の⽴ち上げ・運営に30年余携わる。著書に『認知症ケアの真髄』などがある。
⽂/⾼野千春 イラスト/ホンマヨウヘイ